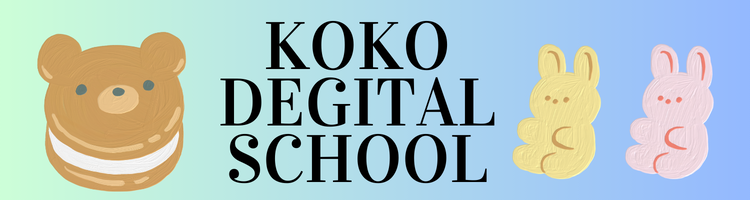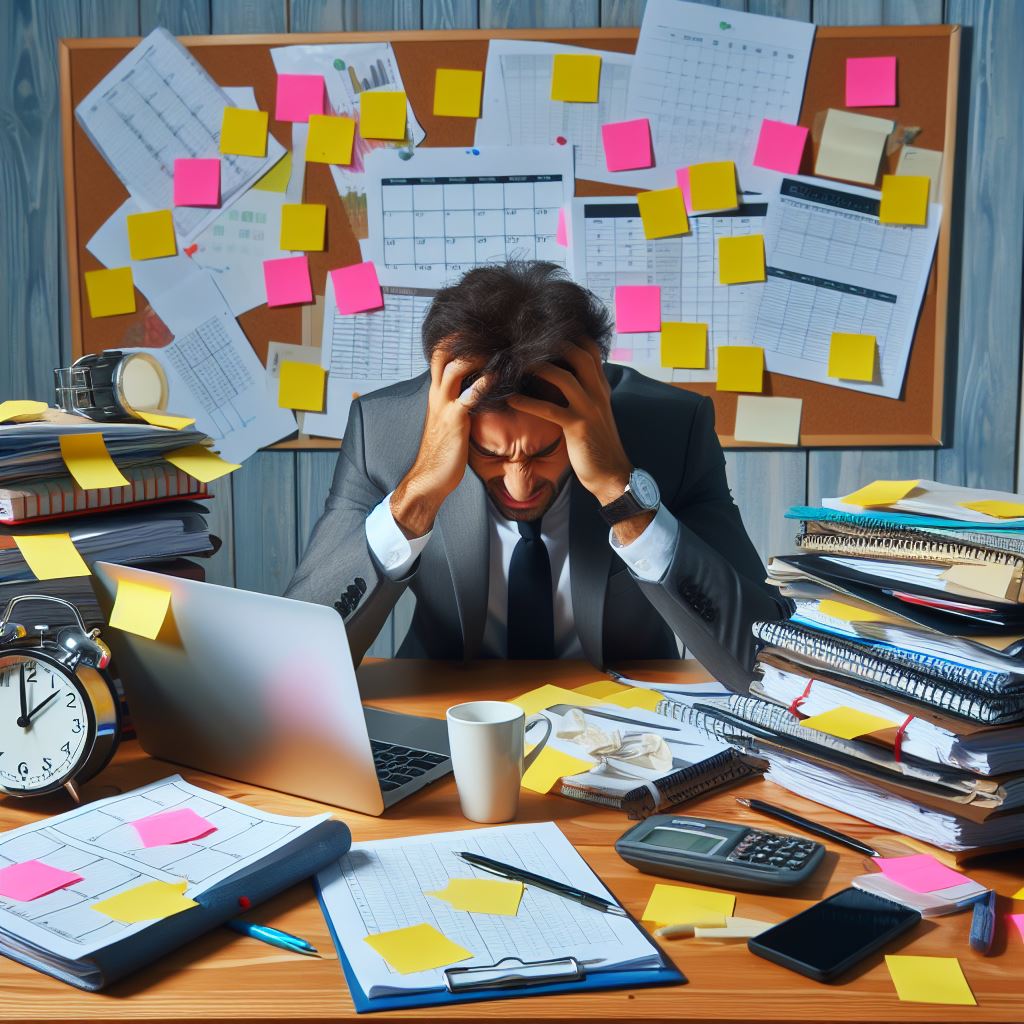
私は企業で仕事しながら、副業でフリーランスとして個人で仕事を請け負っています。
その際、自分と相手のスケジュールツールが異なることがよくあり、日程調整に手間取ることが多々ありました。
ある時、新規のクライアントと打ち合わせを重ねる機会がありました。
しかし、お互いのスケジュール管理ツールがバラバラで、なかなか具体的な日程をフィックスできずにいました。
メールをしたり電話で確認を重ねたりと、調整作業に手間と時間をかけ続けました。
そうこうするうちに、結局作業自体に取り掛かれる時間が少なくなってしまいました。
価値を生む本来の業務よりも、日程調整に時間を取られ続けた結果、時給ベースで考えると無駄な時間が多く生まれてしまったのです。
フリーランスは時間とエネルギーを無駄にできません。
しかし、ツールの違いが原因でスムーズな日程調整ができない状況は、生産性を著しく低下させてしまうことが分かりました。
作業時間は限られているので、本来の価値創出に集中することが何より大切なのです。
このような経験から、効率的で相互運用可能な日程調整ツールの必要性を強く感じるようになりました。
そこで本記事では、「スケジューリング力」を高める7つのステップをご紹介します。
個人でも組織でも、この力さえ身につけていれば、時間とエネルギーを無駄にすることなく、適切なタイミングで適切なアウトプットを出せるようになります‼
スケジューリング管理力とは?時間を味方につける力
スケジューリング管理力とは、自分やチームの行動を効果的に調整し、時間を最大限活用する能力のことです。
時間は有限な資源ですから、期限や優先順位を意識しながら、無駄なく賢く使いこなせる力が不可欠になります。
単に予定をこなすだけでなく、行動と行動の間の隙間時間まで意識的に使える人こそ、真のスケジューリング管理力の持ち主と言えるでしょう。
時間を味方につけられる人は、自分の可能性を最大限に引き出すことができるのです。
まずは隙間時間の見える化からやってみることをお勧めします‼
仕事中などの隙間時間にすぐ見れるインプットメモ帳作った。なかなか良い感じ👌#危険物 pic.twitter.com/USniC9HjFG
— またたび (@matatab65581268) April 23, 2024
ゴールを明確にせよ – 目的意識の重要性
物事を進めていく上で、最も大切なことは「ゴール」を明確にすることです。
しかし、ただゴールを立てるだけでは不十分です。
重要なのは、そのゴールが本当に自分が得たい”真のゴール”なのかを見極めることです。
私は因果連鎖を分析することで、ゴールの奥にある根本的な目的や動機を振り返る習慣があります。
表面的なゴールにとらわれすぎると、本質を見失ってしまう恐れがあるからです。
例えば、会社の業績アップをゴールに掲げても、それ自体が最終目標なのでしょうか?
本当は従業員や家族の幸せを追求したいから業績アップが必要なのかもしれません。
このように因果関係を掘り下げることで、自分が何を本当に大切にしているのかが見えてきます。
ゴールを明確にするだけでなく、そのゴールの背景にある”真のゴール”を認識することが何より重要です。
そうすれば、その先に待つ課題の対処法も自ずと見えてくるはずです。
一人ひとりが同じ最終ゴールを共有し、そこに向かうことで、チームの力を結集することができるのです。
仕事と生活の調和を図る – ワークライフバランス
ミッドライフ・クライシスと呼ばれる人生の中途半端な時期に、多くの人がワークとライフのバランスを失ってしまいます。
家族との関係性の変化や、自身の価値観の揺らぎから、人生の意味や方向性に疑問を持つ人が増えます。
しかし、そこで多くの人が陥りがちなのが、「仕事の忙しさ」と「家庭の責任」のどちらかに極端に振れてしまうことです。
仕事に没頭し過ぎれば、家族や自分の時間が犠牲になり、心身の健康を損ねかねません。
一方で家庭優先に切り替え過ぎれば、今度は自己実現の機会を失い、焦りや不安に駆られます。
このジレンマを解決するには、「スケジューリング管理力」によるワークライフバランスの実現が不可欠です。
仕事と生活の調和を意識的にコントロールできる人こそ、豊かな人生を送れるのです。
上手くスケジューリングすれば、仕事で成果を上げつつ、プライベートも充実させられます。
お互いが好循環を生み出し、リフレッシュした心身は更なる生産性の向上にもつながります。
ミッドライフ・クライシスに揺らぐことなく、人生の各領域を豊かに保ち続けられるよう、ワークライフバランスを意識的に作り上げていきましょう。

優先順位をつける勇気 – タスクの選別が肝心
日々の仕事や生活では、さまざまな「やるべきこと」が山のように押し寄せてきます。
ですが、時間は有限です。
そこで重要になってくるのが、タスクの優先順位を適切につける力です。
できることならすべてをこなしたいものですが、現実にはそうもいきません。
本当に大切なことに集中するには、そうでないものに対しては「NO」と言う勇気が必要不可欠なのです。
優先順位の高いものから着手し、低いものは削ぎ落としていく。
これができれば、スケジューリングはグンと楽になります。
小さな習慣からはじめる – 習慣化こそが鍵
大きな目標に向かうには、小さな習慣づくりから始めましょう。
新たな行動を1日や1週間で身につけようとしても無理があります。
継続できなければ意味がありません。
そこでおすすめなのが「ごく小さな習慣」づくりです。
例えば朝10分早く起きる、昼休みに数十分運動する、就寝前にタスクリストを作る…などの小さなことから始めてみてください。
習慣化のコツは、自分のペースで続けられる量から始めることです。
やがてそれらが積み重なり、大きな力となって現れてくるはずです。
定期的な見直しを忘れずにスケジューリング管理もある程度やり続けると、マンネリ化して実効性が落ちてくることがあります。定期的に、自分のやり方を見直すことが欠かせません。
まずは現状の課題を洗い出し、改善できる部分を探ります。
そこから目標設定し、より良い方法を試します。
新しい習慣を取り入れるのも有効です。このサイクルを回すことで、常に最適なスケジューリングを維持できるようになります。
見直しの際は、スケジューリングだけでなく、「ゴール」や「優先事項」の方向修正も行うことをおすすめします。
環境の変化に合わせて、そこに軌道修正を加えていく。これができれば、いつまでも前を向いて歩んでいけるはずです。

テクノロジーを味方につける
昨今のテクノロジーの進化により、スケジューリングを助ける様々なツールが登場しています。
私が紹介したいのは「Spir(スピア)」です。

SpirはGoogleカレンダーなど複数のスケジュールツールと連携でき、オンラインで手軽に日程調整と会議URLの発行・登録ができるサービスです。
従来の面倒な調整作業を自動化し、時間の無駄をなくしてくれます。
さらにSpirは、調整時の絶妙なタイミングで参加者にリマインドを送ってくれる機能も備えています。
設定次第では、会議前後のタスク記録なども可能です。立場や用途に合わせて柔軟にカスタマイズできるのが魅力です。
テクノロジーを味方につければ、スケジューリング管理もぐっと効率化できるはずです。
日程調整にはかなりペインを感じてるんだけど、Spir(スピア)が最高だった。元々使ってたツールと比較してだいぶ高機能で、さらに(今は)無料という。https://t.co/zzIJmToRlL
— 小出 悠人 (@yuto_koide) February 10, 2021
Spir いいな〜〜〜!!!、とりあえず URL 送ればいい感じに日程調整が完了するので本当に助かる / Spir(スピア) | 日程調整ビジネスカレンダー https://t.co/wzNJJEgHm0
— しゅんけー (@shunk031) July 15, 2022